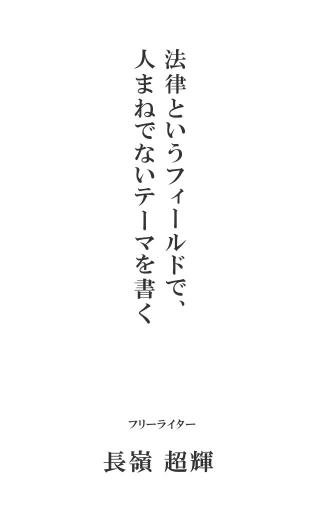法律というフィールドで、
深く、面白く、人まねでないテーマを書く。
長嶺超輝さんは長崎県生まれ、大学卒業後に弁護士をめざし、7年間挑み続けるも挫折、29歳の時に上京し、得意分野を生かして法律・裁判ライターとしてご活躍されています。2007年に『裁判官の爆笑お言葉集』で作家デビューされ、30万部を超えるベストセラーとなります。『裁判官の人情お言葉集』『サイコーですか?最高裁!』『罪と罰の事典 ― "裁判員時代"の法律ガイド』などやわらかめの法律関係のご著書も多い長嶺さんに、本について、電子書籍についてのお考えをお伺いしました。
取材は東日本大震災とネット犯罪の二本柱。
――早速ですが、近況を伺えますか?
長嶺超輝氏: 東日本大震災以来、東北を中心に裁判の取材へ行くのをライフワークにしています。原発関係者への脅迫や、「放射性物質が体外に排出される」とうたって健康食品を勧める薬事法違反の事案、あるいや義援金詐欺や窃盗などが散発的に起きているので、法廷という場を通じてそれらの実態を独自に調べていますね。裁判取材に関しては、東日本大震災や原発事故に付け込んだ犯罪と、インターネット犯罪の2本柱でやっていますが、ネット犯罪の傍聴記録は、今のところ書籍の原稿になる予定はありません(笑)。ほかの近況としては、執筆活動と並行してネットショップで物販業を運営しつつ、電子書籍のダウンロードに誘導するようなサイトにしたいのですが、始めたばかりなのでこれからです。
――どちらかというと電子書籍がメインということでしょうか?
長嶺超輝氏: できればオリジナル電子書籍のダウンロードサイトを作ろうかと考えていますが、それだけではなかなか人が集まらないので、物販と一緒に組み合わせてやろうと思いました。この場所(取材現場)にネットショップの在庫を置かせてもらっているんですが、じつは私の著書の読者でいてくださっている社長さんの事務所兼作業場を使わせてもらっていて、とても有り難く思っています。また、自分の原稿を書くだけでなく、本を出したい方の支援をすべく、NPO法人「企画のたまご屋さん」で出版プロデューサーをしています。
――出版プロデューサーという仕事は具体的にはどのようなお仕事をされるのでしょうか?
長嶺超輝氏: 出版したい企画を持っている方を、出版まで支援するエージェントのような業務です。サイトに応募があった多数の出版企画の中で、内容に具体性があって、プロフィールに一定の説得力があり、需要の見込みがあるというものについて、各自の判断で担当に立候補します。担当した企画に助言・修正をして下準備をした後、数百名の出版社の編集の方へ向けて一斉配信されます。その中で、ある編集者から編集会議にかける検討をしたいとの「オファー」がきたなら、編集者との打ち合わせに同行したり、首都圏以外にお住まいの方については打ち合わせを代行したりして、面白くて有意義な本を一冊でも多く世に出すため、出版までの道のりを支援しています。
私はたまに「読者として読んでみたい」と純粋に思った企画、オファーは来ないかもしれないけれどもユニークで情熱を感じる企画も勢いで担当するんですが(笑)、
九州大学法学部から弁護士をめざす。
――本日は読書のインタビューということで、幼少期からさかのぼって読書との関わりをお伺いできればと思います。どのようなお子さんでしたか?
長嶺超輝氏: 今、実家は出身地の長崎・平戸市に戻っていますけれども、3歳くらいの頃に熊本に引っ越して、高校まで熊本で過ごしました。家で本ばかり読んでいる、協調性がない子どもだったような気がします。この世の中がどういうふうにして動いているのかに、漠然と興味があったんですが、社交性は欠けているという残念なお子さまです(笑)。昔から文字や数字に興味があって、本に限らずチラシから説明書、電話帳、食品のパッケージ、母子手帳まで隅から隅まで読んでいました。父のクルマに乗っているときは、ずっと窓の外を見つめて、街中の看板を見つけるたびに指さしては、そのまんま声に出して読んでいたので、特に母親から呆れられていました(笑)。
――印象に残っている本はありますか?
長嶺超輝氏: 親が買ってくれた百科事典や昔話の本を読んでいました。中でも子ども百科事典の第11巻の「物の名前図鑑」が大好きで、その1冊ばかり脇に抱えて屋外へも持ち歩いていたので、表紙も外れて、もう中身しか残っていないくらいになっていましたね。
――実際に「自分で書く」のはいつから始められましたか?
長嶺超輝氏: 幼稚園から漫画のようなものを描いていました。小学校でもテストの問題が解けない時に、潔くあきらめてテスト用紙の裏に暇つぶしで絵を描いたり、友達を登場人物にしてレーシングや歴史などがテーマの漫画を描いたり、ゲームブックを作ったりしていましたね。人見知りなので、漫画を通じて友達とコミュニケーションをとるようなことをしていたら、いつの間にか漫画のノートがなくなったことがあって、探していたら、別のクラスで回し読みされていたんですよね。その漫画の人気が出て、浮動票で学級委員に選ばれてしまったこともありますが、クラスで最も忘れ物が多くて、社会科見学では展示物に見とれて列から外れる、まったく頼りない学級委員で(笑)。高校時代には、映画研究会でオリジナルの脚本も書いていました。
――高校まで熊本で過ごされて、そこから九州大学の法学部へ進まれますね。
長嶺超輝氏: 小中は一応テストの点は良かったのですが、高校は進学校で、熊本じゅうから賢い感じの生徒が集まっていましてね。最初の中間試験で500人中450番になってしまい「これではいけない」と、ふんどしを締め直しました。その高校では450番以下は死後の世界、430番は黄泉の国、501番はリーバイスと揶揄されていまして(笑)、いや、揶揄かどうかわからないですが、そんな調子の環境だと、嫌でも勉強するしかないですよね。せめて「黄泉入り」は回避しようと(笑)。もともと宇宙とか恐竜とか、デカいモノに興味がありまして、天文学者か地震学者になりたいという思いもあったので、理学部へ行きたかったのです。しかし、残念ながら計算が大の苦手で、「お前は理系コースはだめだ」と物理の教師に言われ、漠然と文系へ進むことにしました。大学は、なんとなく自由なイメージがある京都大学へ行きたかったのですが、なかなか実力不足で手が届きませんでした。二者面談で「京大はやめておけ」と、担任から正式にティーチャーストップがかったんですよね(笑)。定期試験の成績が校内でだいたい150番内につけていれば九大を狙っていいという状況でしたので、そのレベルだけは確保しようと。
――弁護士になろうと思われたのはどうしてでしょうか。

長嶺超輝氏: 「就職に有利」という消極的な理由で法学部へ入ったので、しばらく法律そのものに興味は持てませんでした。でも大学2年のときの民法の講義で、不動産の「二重譲渡」という問題の解説を聴いたのが転機となりました。ある土地について、AさんがBさんに売り、さらにCさんにも売った。この場合どうなるか?という法律問題で、正解は、BさんとCさんのうち、不動産移転登記を先に済ませたほうが所有権を取得する。つまり、早い者勝ちなのです。「早い者勝ちってなんだよ。法律はいい加減だな」と思いましたが、「でも、いい加減さが面白いな」と。じつは早い者勝ちという結論も、両者間の公平を保つ法的処理のひとつなんですよね。その流れで、大学3年になって民法のゼミに入りました。入った後にそのゼミが九大法学部で一番厳しいゼミだと知りましたが、時すでに遅し。ゼミの担当教授は大学4年時に司法試験に受かったそうなのですが、司法修習生の研修中に「やっぱり違うな」と思い、学者に転身したような人でした。当時は司法書士事務所でアルバイトもしていたんですが、その先生からから居酒屋の席で「長嶺君の思考回路は、司法書士というより弁護士向きなんじゃないか」という風に言われて、「そうかなあ」と、だんだんその気になり始めました。書店の司法試験コーナーで、立ち読みで憲法のマークシート問題を2問解いたら両方正解だったので「もしかして、いけるんじゃないの?」と思ってしまったのが間違いの始まりでした(笑)。
ツテもコネもなかったけれど、自信だけはあった。
――司法試験を断念した後、上京してライターになろうと思われたのはどのようなきっかけだったのでしょうか?
長嶺超輝氏: もし弁護士になったとしても、一般読者向けに法律に関する本を出したいとは思っていたんです。結局、弁護士資格は取れなかったけれど「今まで、ひたすら司法試験という悪魔に魂を売ってきたぶん、これからは好きなことをやろう」ということで、29歳でなんのあてもなく上京したんです。司法試験に関しては、自信を完全に喪失していたのに、原稿を書くことに関して、なぜか自信だけはありました。
――そのわずか2、3年後に『裁判官の爆笑お言葉集』(幻冬舎新書)がベストセラーになりましたね。
長嶺超輝氏: ほとんど家出同然の上京だったので、保証人がいらない板橋区のゲストハウスに住んでいました。本来は、日本に旅行中の外国人が格安で一時滞在する宿泊施設なんですが、結局は3年近く居座っていましたね(笑)。企画の売り込みはずっとやっていましたが、企画書を郵送してもまったく反応がなく、出版社や編集プロダクションのライター募集に応募しても、こちらの実績が皆無なので、けんもほろろに断られていましたね。100円ショップやコンビニ、ホームセンターのレジ打ちのアルバイトで食いつないでいました。転機は2005年の郵政解散の際、最高裁の国民審査に関する判断資料となるデータを私が公表したときです。ネット上で結構なアクセス数があって、朝日新聞の夕刊にも取り上げていただきました。それがきっかけで、幻冬舎の編集の方が「面白いことやっていますね、少し話をしませんか」と声をかけてくださって、話をしていくうちに、新書を書いてみないか、という話になったのです。
――お声がかかった時は、どのようなお気持ちでしたか?

長嶺超輝氏: 当然うれしかったのですが、企画案を送るたびに「ちょっと違いますね」という返事が返ってくる、そういったやり取りを半年くらい続けました。これから裁判員制度が始まるという時期だったので、刑事裁判で一連の流れを、一般の人向けに説明する本の企画を練っていたんです。ただ、書くべきテーマがなかなか固まらない。こんな調子が続いたら、新書を出す話も、なし崩しで無くなってしまうんじゃないか、という焦りもありましたね。ですが、そのうち、刑事裁判の流れの終盤にある手続き、裁判官が判決を言い渡す際に、被告人に対して将来の助言をする「訓戒」に注目するようになりました。訓戒の具体例をリサーチするため、過去の新聞記事を調べていたら、裁判官の興味深い発言がたくさん見つかったんですよね。ブログで試しに紹介してみると大きな反響があったので、「裁判官の訓戒だけに焦点を絞って1冊にしませんか」という提案をしてみました。裁判官の言葉を通じていろいろな法制度の背景も知ることができますし、検察側か弁護側、どちらの味方に振れるかわからない。その言葉には独自の世界観があるなと私は感じました。
デビュー作の新書がいきなり30万部超のベストセラーに。
――ベストセラーになった時はいかがでしたか?
長嶺超輝氏: この原稿は面白い、という絶対的な自信はありましたが、ビジネス面での不安はいっぱいでした。「どうしてこんなに売れているのかな」と。しかも、書籍の売れ行きは著者のあずかり知らないところ、肌感覚のない領域でうごめいていて、売り上げ部数の数字ばかりが増えていくので、ちょっと恐ろしいなというのが正直な気持ちでした。本を出して数日後、100円ショップでのアルバイト中に、休憩室でおにぎり弁当を食べているとき「3万部の増刷が決まりました」と、びっくりする報告の電話がかかってきたので、「さすがにもういいかな」と、その日のうちにアルバイトを辞めようと決めて、執筆や取材対応に専念することにしました。感想のメールも全国からたくさん頂きましたし、しばらくは書店で売り切れ続出で、「どこで売っとると?」って、九州の友人や親戚から電話がかかってくるんですが、著者に配本の権限はありませんしね(笑)。大学のゼミの恩師もすごく喜んでくださいまして、東京で定年退官のパーティを開いた際には、『爆笑お言葉集』を大量に買い取って、参加したゼミOB・OGに1冊ずつ配るという粋な計らいをしてくださいました。
――それからいろいろなご本を出版されていますが、長嶺さんはどのような思いで執筆されていますか?
長嶺超輝氏: 司法試験に本気で取り組んだことのあるフリーライターは、まずいないんじゃないかと思います。法律というジャンルの上澄みをすくって書けるライターならいるかもしれませんが、本来は難解な内容をシンプルに説明するには、どうしても絶対的な習得量が必要です。私がどんなに努力しても司法試験に合格できなかったのは、客観的には挫折なのでしょうが、その挫折をアドバンテージとして利用させていただきまして、「法律って、意外と面白いんだよ」ということを、皆さんに知っていただきたいと思います。読み物を通じて、ひとりでも多くの皆さんに、もし「世の中って、捨てたものじゃないな」と思いなおしてもらえるなら、ライター冥利に尽きますね。
満員電車で本を買える電子書籍は、まさに「ドリーム」。
――長嶺さんは紙の本を電子化して、ユーザーが読むことに関してはどう思われますか?
長嶺超輝氏: 出張のときに、何冊も持っていかなくていいわけですから、とにかく便利で、移動時間をつぶすには最高のツールですよね。かさばらないのが一番です。
――書き手として、電子書籍で読まれることについてはどうお考えですか?
長嶺超輝氏: 大事なのは中身だと思っているので、全然こだわりはありません。私自身も電子書籍端末のユーザーですから、電子はけしからんと言う立場ではありません。もともと私は、活字なら何でも手当たり次第に読みあさっていたガキですしね(笑)。
――実際に使ってみていかがでしょうか?
長嶺超輝氏: 読みたい本を、読みたくなったタイミングで、どこでもダウンロードできるのが最高だと思います。紙の本だと、読むのに両手が必要だったのが、電子書籍なら片手で読めるじゃないですか。たとえ満員電車の中で身動きが取れない状態でも本が読める、買えるというのは、読書好きにとって、まさにドリームという感じではないでしょうか。できれば、電子書籍を古本として売れるシステムができればいいなと考えています。読み終わったら要らない本は売って、そのとき、ちょっとだけ著者に利益が還元されるような古本システムがあればいいのですが、電子だとシステム構築が難しいのか、まだ私の知る限りでは実現されていないようです。拙著に関しては、古本屋で買うでも、図書館で借りるでもいいので、とにかく目を通してもらって、もし「この長嶺というライターは面白い」と思ってくれたなら、それを入り口にして新作を購入していただければ有り難いですね。
出版不況、面白いものを書くために「頑張るしかない」。
――今のこの出版の現状について、書き手としてどのように感じられていますか?
長嶺超輝氏: 書き手としては、とにかく面白くて身になるものを世に出すため、リサーチや執筆を頑張るしかないと覚悟しています。私の立場で、何か出版業界に貢献できることといえば、それしかありません。良書を世に出し続ける気概をあきらめたら、いよいよ出版業界は終わってしまいます。
――本は出版社や編集者の方とのやり取りの中からできていくわけですが、その中で編集者はどのような役割を担っていると思いますか?
長嶺超輝氏: 編集者は最初の読者です。最初に原稿を読んでもらい、感想をいただく。この電子書籍時代に、編集者は不要だという人もいますが、私はそうは思いません。書き手や編集者が納得して出版し、読者も納得するような本が、最も幸せなサイクルの中にいると私は思っています。逆に言えば、読者ウケがよくても、著者が納得していない本は、長い目で観察してみたとき、ダメになるのではないかと。
――長嶺さんにとって、編集者とはどのような存在ですか?
長嶺超輝氏: デザイナーや校正者との関係調整など、自分ができないことをやってくださるので、ひたすら有り難い存在です。書き手としては、「素晴らしい」と褒めてくださるだけではなく、原稿がさらに面白くなるよう、私と異なる視点で助言してくださいますしね。
――出版プロデューサーになろうと思われたのは、何がきっかけだったのでしょうか?
長嶺超輝氏: 編集の方から「こういう書き手はいないか?」ということを相談されることがある一方、ある経営者の方から「本を出したい」と相談されたこともあります。それで出版を仲介する立場に興味が出てきたのがきっかけです。私もかつて、ゲストハウスに住み着いていた時代に、どうしても本を出したくて、企画の売り込みを出版エージェントに依頼したことがありました。「前金3万円」と要求されまして、約2か月後にどうにか3万円を用意して会うことができたのですが、原稿を見てもらって、ちょこちょこっと「アドバイス」という名目で、原稿に添削して、「この企画は難しそうだね。バイバイ」というような感じでした。誰も添削なんか求めてねえよと。私は、そんな中途半端なプロデューサーにだけは絶対になるまいと心に誓っています。「企画のたまご屋さん」のように、本が出るまでは無償で、本が出たら印税から運営費としてちょっと頂きますというプロデュース形態は良心的だと思います。企画が通らなくても何度だって挑戦できますしね。
今、3冊を同時に執筆中。
――今後の展望をお伺いします。
長嶺超輝氏: 今、本を3冊、並行して執筆しています。1つ目が弁護士の暑苦しい法廷弁論集で、9月に出る予定です。2つ目が憲法の本で、「もしこの憲法のこの条文がなかったらどういう世の中になるのか」というシミュレーションをしたものとなっています。3つ目が冒頭でお話しした東日本大震災の犯罪に関するルポ。このほかにも各社に打診中の企画がありますが、それは編集会議を正式に通ってからでないと、ペラペラしゃべれません(笑)。今までに誰も読んだことのない感覚の内容、書き終えた後に「俺って、こんなことを考えていたのか」と、自分でも驚くような原稿が仕上がるよう、常に気を張って書いています。経験上、どこかで見かけたようなありきたりの企画だと、原稿を書く気が8割ほど減ってしまうので(笑)、私は人まねが苦手なようです。どうせパクるのなら、本に限らず、番組、記事、会話、広告、道ばたで見かけた変な人など、世の中に転がっている興味深い要素や多彩な工夫を何百個も寄せ集めて、これらのヒントをひとつに結実させたい。今までに誰も手を付けていない領域へ、頭を突っ込んで進めていくほうが性にあっているのかなと思います。それと、文章を書くのに苦手意識がある人へ向けて、書く楽しさを伝授するような取り組みも新たにやってみたいですね。

(聞き手:沖中幸太郎)
著書一覧『 長嶺超輝 』